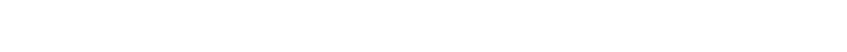婚前契約とは?いま独身のスタートアップ経営者へ届ける婚前契約の知識

1 はじめに
既婚者が会社を設立する際、出資金や取得した株式も夫婦の共有財産とみなされる可能性があり、万が一、離婚という事態が生じた時には、会社の株式持分の半分が配偶者に分与され、会社経営に無関係な元配偶者が大株主になってしまうリスクがあります。この場合、会社の経営権が脅かされ、資金調達やExitの場面にも悪影響を及ぼしかねません。特にスタートアップでは資本政策の観点からもこのリスクを回避することが重要です。
こうした株式分与リスクへの主な対策として注目されているのが、「婚前契約」(民法上は「夫婦財産契約」)を活用する方法です。
以下では、海外の事例を交えつつ、婚前契約の仕組みや作成ポイント、そして婚前契約がない場合に婚姻後に取得した株式が抱えるリスクについて解説します。
2 海外スタートアップにおける離婚と株式分与の事例
アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏は、離婚に際して保有していたアマゾン株の約4兆円相当(約2,000万株)を元妻マッケンジー・ベゾス氏に譲渡しました。マッケンジー氏はこの離婚で世界長者番付に名を連ねるほど巨額の株式を取得しました。
また、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏も結婚から27年後に離婚を発表し、婚前契約は結んでいなかったものの話し合いにより資産分割の合意に至ったと報道されています。
アメリカでは富裕層や起業家に限らず婚前契約(Prenuptial Agreement)を結ぶカップルが少なくなく、ある統計では全体の約5%が婚前契約を締結しているともいわれます。
他方、日本では婚前契約の文化が根付いておらず、利用例自体が非常に少ないのが現状です。しかし近年では、日本のスタートアップ業界でも徐々に婚前契約を結ぶ創業者が増えつつあるようです。
3 婚前契約の法的仕組み
婚前契約とは、文字通り婚姻前に夫婦となる二人が結ぶ契約で、婚姻後の財産の取り扱いや離婚時の財産分与のルールなどを定めておくものです。日本でも法律上この契約を結ぶことは可能であり、民法上は「夫婦財産契約」として位置付けられています。
婚前契約において重要なのは、婚姻届を提出する前に締結しなければならないという点です。これは、民法第754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」と規定されており、婚姻後に夫婦間で交わした契約は原則としてどちらか一方の意思で一方的に取り消せてしまうためです。
(なお、2024年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、民法第754条は削除されることとなりました。施行はまだ先のことですが、この改正によって、必ずしも婚姻前ではなく、婚姻後でも夫婦間の財産契約は有用なものとなります。)
婚前契約は婚姻後に内容を変更することができません。この不可変更性ゆえに、契約内容は慎重に検討する必要があります。また、婚前契約は夫婦間の合意さえあれば、基本的に自由に内容を定めることができます。
ただし、一方にあまりにも不利・不平等な条項(例:「夫婦の全財産は常に夫のものとする」等)や離婚そのものを強要するような条項は、公序良俗違反や契約の趣旨に反するとみなされ無効となる恐れがあります。契約条項が複数ある場合は、一部の条項が無効でも契約全体が無効にならないような分離条項を入れておくことも一般的です。
もっとも、せっかく婚前契約を結んでも、第三者(相続人や債権者など)にその契約内容を主張できなければ万全とは言えません。
婚前契約の内容を第三者に主張するためには、「夫婦財産契約の登記」をしなければならないと法律で定められています。この登記を行うと契約内容が公の記録となり、誰でも閲覧できる情報になります。登記がない場合、第三者は夫婦間の契約内容を知り得ず「善意の第三者」となってしまうため、契約で決めた内容を対抗できません。
第三者からの請求に備えるためには、本来は婚前契約自体を公証人の認証の上で登記しておくことが望ましいとされています。
4 婚前契約に盛り込むべき内容と株式保全のポイント
スタートアップ創業者が婚前契約を活用して自己の保有する自社株を守る際の最大のポイントは、創業者の保有する自社の株式を財産分与の対象から除外する旨を明確に取り決めておくことです。
また、婚姻前に保有していた財産を原資として婚姻後に取得・設立した会社の持分や株式は、たとえその価値が上昇したとしても夫婦共有財産には含めないことについて明記することも重要です。こうすることで、万が一離婚となった場合でも、自社の株式は財産分与の対象から除外され、会社経営への悪影響を避けることができます。
なお、事業資金の出所を明確に分けておくことは後々の紛争予防に役立ちます。すなわち、会社設立や増資に充てる資金は婚姻前から保有する預貯金や資産から拠出し、夫婦の共有財産と混同しないようにします。
こうすることで、婚姻後に取得した財産でも、その原資が婚姻前からの特有財産であれば原則としてその取得財産も特有財産として扱われ、離婚時の財産分与の対象から除外されます。
5 婚姻後に株式を取得・会社設立する場合の注意点
最後に、会社設立後に婚姻するケースや婚姻後に株式を取得した場合のリスクについて触れておきます。
前述のとおり、婚姻中に形成した財産は原則共有財産となるため、たとえ婚姻より先に会社を起こしていても、婚姻後に追加取得した株式や新たに受け取ったストックオプション、増資による持株比率の変化部分などは共有財産とみなされる可能性があります。
特に婚姻後の収入や夫婦共同の預貯金から出資した株式は、婚前契約が無ければ確実に共有財産とみなされる可能性が高いです。また、婚姻後に会社を設立する場合は、特有財産からその資金を拠出し、そのことを明確化しておくことが望ましいです。
そのうえで、婚前契約を締結し、株式を共有財産に含めない取り決めをしておくことでリスクを大幅に低減できます。
将来的に婚姻の予定がある起業家は、ぜひ婚姻前の早い段階で専門家に相談し、必要なら婚前契約の準備を進めることを強くお勧めします。
当事務所(S&W国際法律事務所)でも起業家・経営者の婚前契約に関するご相談を承っております。
婚前契約を適切に活用して大切な会社と将来の財産を守り、安心して起業や結婚に踏み出せるよう、ぜひ専門家の力を積極的に活用してください。
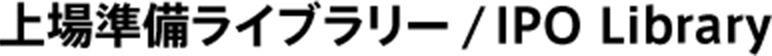
 S&W国際法律事務所
S&W国際法律事務所